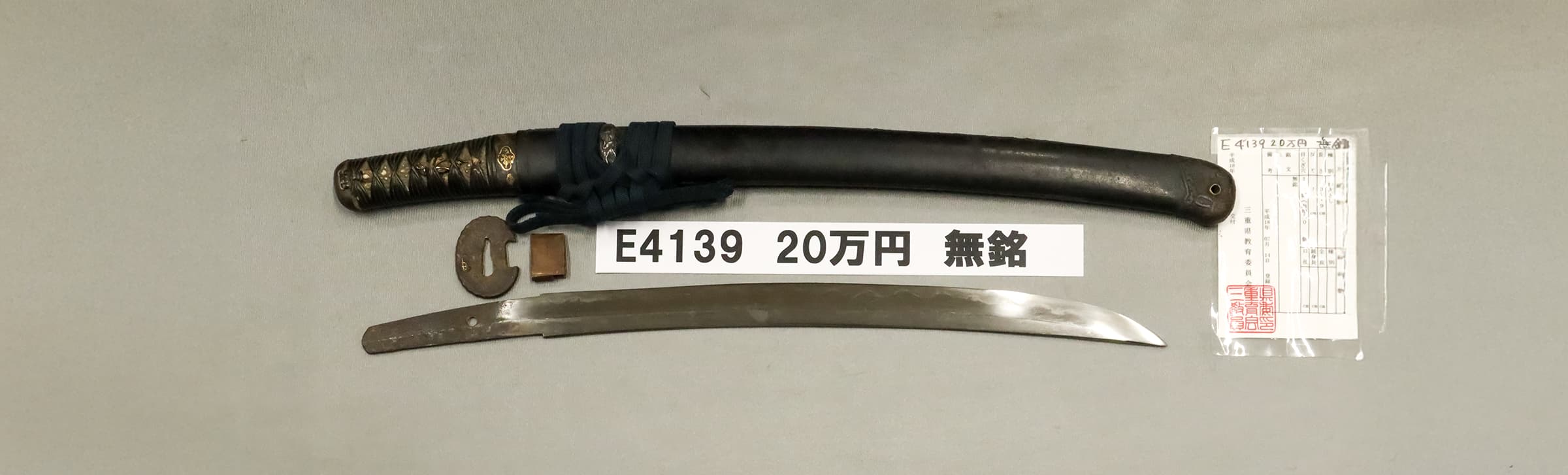E4139【拵付脇差】無銘
室町時代中期(15世紀頃)に製作されたと考えられる無銘の拵付脇差です。刀身は、鎬造の変化型である「菖蒲造(しょうぶづくり)」で、切先から棟にかけて鋭く延びる姿が特徴的です。これは、戦場での突き刺し性能を高めるために考案された造り込みで、戦国期の実戦刀として高く評価されています。地肌は板目肌が詰み、互の目乱れの刃文が連なり、時代を経た趣ある姿を見せています。
茎(なかご)は生ぶで、栗尻形、ヤスリ目は経年により判別しにくくなっていますが、丁寧な造りがうかがえます。銅製のハバキを備え、外装は鐺(こじり)付き黒塗時代鞘、革巻柄といった質実剛健な拵えでまとめられており、当時の実戦武士が携えた姿を今に伝えます。
室町中期は応仁の乱(1467年)をはじめとする群雄割拠の時代で、多くの刀匠が実戦向けの刀を打ち続けました。菖蒲造の脇差は比較的希少で、戦国時代の荒波を生き抜いた証といえるでしょう。
実用刀としての鋭さと美術品としての風格を兼ね備えた、戦国ロマン漂う一品です。
-
- 銘
- 無銘
-
- 時代
- 室町時代中期
-
- 刃紋
- 乱
-
- 目釘
- 1
-
- 重量
- 278g
-
- 刀長
- 37.9cm
-
- 反り
- 1
-
- 元幅
- 2.8
-
- 元重
- 0.5
-
- 先幅
- 2
-
- 先重
- 0.3
-
- 登録番号
- 三重県 第50972号
-
- 登録年
- 平成18年