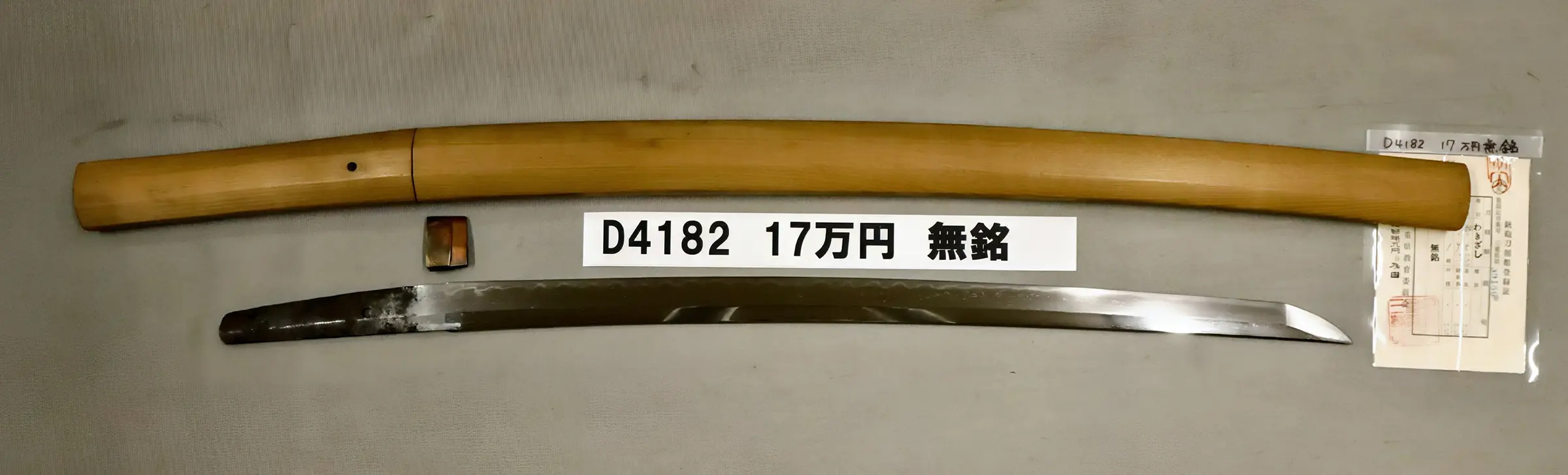D4182【白鞘脇差】無銘
江戸時代初期(17世紀初頭)に製作された無銘の白鞘脇差です。鎬造・庵棟の典型的な造りで、板目肌がよく流れ、地鉄には力強い動きが見られます。刃文は互の目乱れが連なり、沸の輝きが随所に感じられる華やかな仕上がりです。大切先に仕立てられた姿は堂々としており、巾広でどっしりとした重量感が、当時の実戦期の作であることを想起させます。
茎(なかご)は生ぶ(生茎)で栗尻、平行なヤスリ目が整い、時代の自然な錆色を保っています。銅二重ハバキが丁寧に合わせられており、長年の保存状態も良好で、さび・刃こぼれも見られない健全な刀身です。
江戸初期は戦国の動乱が収まり、武家社会が整う中で、実用刀から美観を重んじる刀剣へと変化が進んだ時代。本脇差は、その過渡期の特徴をよく示しており、豪壮さと品格を併せ持つ一振といえるでしょう。無銘ながら、刀工の確かな技量を感じさせる逸品です。
-
- 銘
- 無銘
-
- 時代
- 江戸時代初期
-
- 刃紋
- 乱
-
- 目釘
- 1
-
- 重量
- 516g
-
- 刀長
- 54.5cm
-
- 反り
- 0.9
-
- 元幅
- 3
-
- 元重
- 0.6
-
- 先幅
- 2.1
-
- 先重
- 0.5
-
- 登録番号
- 三重県 第39186号
-
- 登録年
- 昭和51年