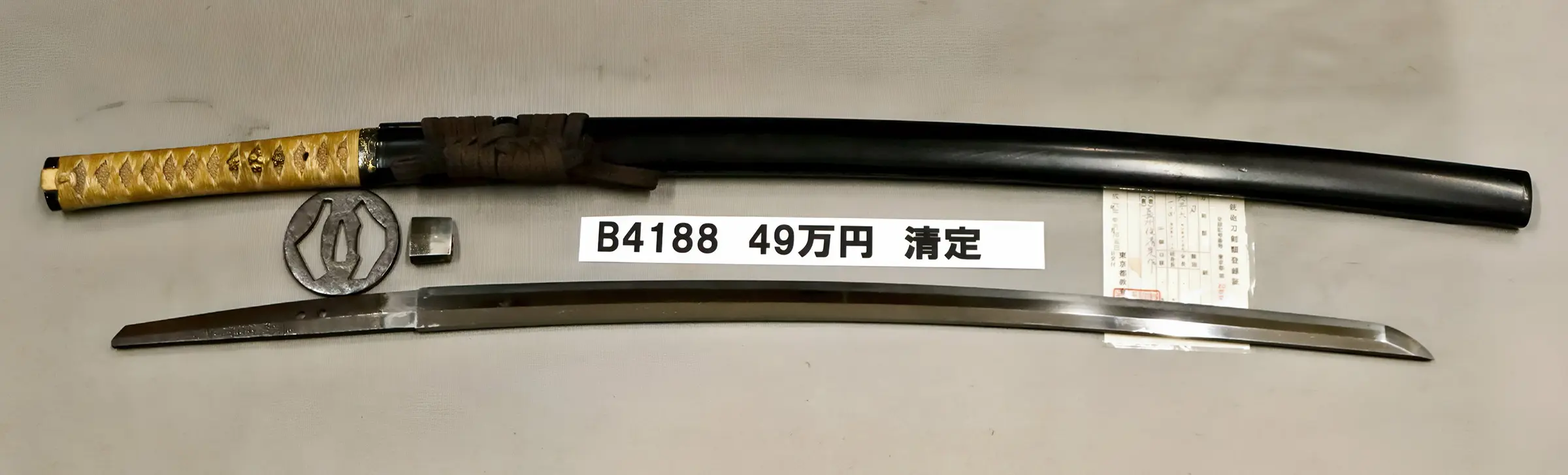B4188【拵付刀】清定
「長州住清定作」と銘を刻む、江戸時代中期の拵付刀です。清定は長州藩(現在の山口県)で活躍した刀工で、萩鍛冶の一派に属すると伝えられます。長州藩では幕府に仕える武士の需要に応じ、実用性と美観を兼ね備えた刀が多く作られましたが、本刀もまさにその代表格といえます。
地鉄は板目に杢目が交じり、よく練れて冴えた地景を見せます。刃文は乱れこころに足入り、柔らかさの中に力強さを感じさせる見事な出来。中切先で姿は引き締まり、全体の均衡が優れています。茎(なかご)は生ぶで剱形、丁寧な仕立てが刀工の技量を物語ります。銀祐乗のハバキ、黒塗り艶鞘、丸形透かし鉄ツバと、拵も上品で落ち着いた佇まい。保存状態も良く、さび・刃こぼれのないほぼ欠点のない状態です。
江戸中期、泰平の世にあっても武士の魂として鍛えられた清定の一振り。実用刀としての確かさと、美術刀剣としての美しさを兼ね備えた逸品です。
-
- 銘
- 清定
-
- 時代
- 江戸時代中期
-
- 刃紋
- 乱
-
- 目釘
- 2
-
- 重量
- 738g
-
- 刀長
- 63.6cm
-
- 反り
- 1.4
-
- 元幅
- 3
-
- 元重
- 0.8
-
- 先幅
- 1.9
-
- 先重
- 0.5
-
- 登録番号
- 東京都 第266819号
-
- 登録年
- 平成6年