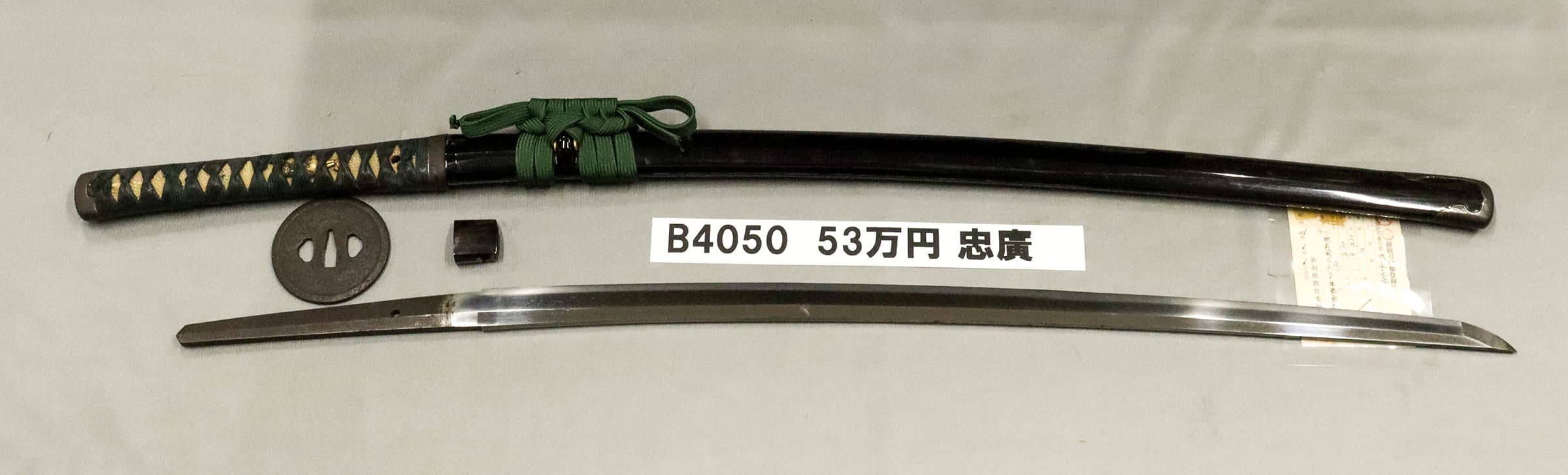B4050【拵付刀】忠廣
江戸時代初期を代表する名工「肥前国住近江大掾藤原忠廣」による拵付刀です。忠廣は、初代忠吉の子として肥前佐賀藩に仕え、初代の精緻な作風を継承しながらも、より洗練された安定感のある刀姿を確立したことで知られます。江戸初期は徳川の治世が安定し、刀剣が戦場の道具から、武士の格式や教養を示す美術品へと変化していった時代でした。
本刀は鎬造・庵棟の端正な姿で、小糠肌と称される精緻な地鉄が美しく、刃文は直刃に足が入り、柔らかな中にも冴えを見せる上品な仕上がりです。中切先も整い、見る者に落ち着いた気品を感じさせます。生ぶ茎には「肥前国住近江大掾藤原忠廣」と銘が刻まれ、正統な系譜と確かな作刀技術が裏付けられています。
拵は黒塗のツヤ鞘に丸形の鉄ツバを備え、実用と美観の両立が図られた構成。銅ハバキとの取り合わせも渋く、刀身の格調高さを引き立てています。刃こぼれや錆もなく、保存状態は良好です。
肥前刀工群の名声を高めた忠廣の技が凝縮された一振。鑑賞用としてはもちろん、コレクションにも最適な、江戸初期の名品です。
-
- 銘
- 忠廣
-
- 時代
- 江戸時代初期
-
- 刃紋
- 乱
-
- 目釘
- 1
-
- 重量
- 798g
-
- 刀長
- 69.4cm
-
- 反り
- 1.2
-
- 元幅
- 3.1
-
- 元重
- 0.9
-
- 先幅
- 1.9
-
- 先重
- 0.5
-
- 登録番号
- 新潟県 第16337号
-
- 登録年
- 昭和26年